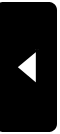2015年08月07日
防災ピクニック開催しました!
お久しぶりの更新です!
子どもたちが夏休みに入り、フル稼働なママも多いのではないでしょうか(笑)毎日お疲れ様ですm(__)m
さて、tasukiでは8/3(月)に防災部で参加者を集ってピクニックをしましたよ。
その名も「防災ピクニック」!

昨年より「ママのための防災講座」を定期開催しているtasuki。
いろいろと勉強する中で、野外のアウトドア経験が防災力アップにつながるなー!ということを感じていました。
そんなわけで、この夏休みの機会に、子どもたちと一緒にお試しで防災ピクニックをしてみよう!というのがきっかけです。
いやー。当日は暑かったけれど、楽しかったです!!
大人は8名。子どもは1歳から8歳の17名。合計25名が集まりました。
場所は長泉町にある『桃沢野外活動センター』。敷地内には桃沢川が流れ、川遊びの誘惑にチラチラひかれつつ(笑)、ピクニック開始です!
カマドに火を起こしたり。

男の子達が火の番人を自ら引き受けてくれました。頼もしい!
ハイゼックス炊飯袋を使って、お米を炊いたり。

白米の他、変わり種ご飯も炊いてみました!
(トマトジュースでリゾット風、塩昆布、コーン缶とツナ缶とコンソメでピラフ風など)
※ハイゼックス炊飯袋とは、災害時に最小限の材料で炊き出しできる魔法の炊飯袋と言われています。保存期間が長く、持ち運びに便利。袋から直接食べることもできるので、食器や箸が不要なのが特徴。大鍋で一度に何袋も炊き出しするのに便利な防災グッズ。
そうそう。参加してくれた子の中には、あらかじめ、おうちでピラフのレシピを書いて持ってきてくれた子もいました。優秀~!!
ついでに、おかずもハイゼックス炊飯袋で調理してみたり。


今回は、自宅にある缶詰を持ち寄って、それらと当日刻んだ人参・玉ねぎ・じゃがいもを組み合わせて何種類かのおかずを作ってみました。
この日は鶏ジャガや、ミネストローネ、王道のカレーなどを作りましたよ。
そうして袋ごと鍋に投入!

30分くらいグツグツしたら、出来上がり!

見た目はちょっとアレですが^^;
なんとかできあがりました!
火にかける時間が足りなくて、芯のあるご飯になってしまったものもありましたが、そんな芯飯を物ともせず、子どもたちはパクパクパクパク…
野外で食べる特別感が、そうさせるのでしょうか(@_@)
とにかく、多少、芯があっても結構イケル!ということが実証されました(笑)
またもう一つ、実証されたことが。
それは、
「カレーは万能!」
ということです。カレーが出てきた途端、子どもたちの食欲は倍増!ママ達も、その安心感に「やっぱりカレーは必須だね」と一同納得でした。
こういった野外のお楽しみイベントでさえ、そうなのだから、災害時は特に、食べなれたものを口にすると、安心感が増すよねーという話も出たりしました。
さて。
食後はちょっとしたお楽しみも用意しましたよ。
その名も「防災スタンプラリー」です。
内容は、
子どもたち一人ひとりにカードを配り、自分の身元情報(名前・年齢・住んでいる場所など、年齢に応じて項目を決めました)を参加者の大人に伝え、正確に伝えられたら、一人につき一つのサインをもらう。順次大人を回って、スタンプを集めたら景品(お菓子)と交換!というものです。

災害時、両親と離れてしまったとしても、こうして自分のことを近くにいる大人に伝えることができたら、いち早くお父さん・お母さんと再会できるきっかけになることは言うまでもありません。
子どもたちにとっては、この日初めて会う大人もいる中、また慣れないこともあって、最初はモジモジしてしまう場面もありました。
でも、お兄さん・お姉さんの姿に触発されて、頑張って伝える子どもたちの姿も見られて、良かったです☆
その他、「大声を出してみよう」「ホイッスルを吹いてみよう」ということで、野外で思いっきり声をだし、ホイッスルを吹いてみたりして、助けを呼ぶ練習もみんなでしてみました。
なかなかおうちではできないことですが、野外でみんなと、まずはやってみよう!と。
ホイッスルは、空気を出す穴をおさえてしまって、うまく音が出せなかったりする子もいました。
やはり、試してみないとわかりませんね~。
ほかにも、防災グッズの中で、持ってはいるけれど、使ったことがない!というものも、使ってみないと分からない使用感など、きっとありそうですね。。。
とにもかくにも、こうして楽しみながら訓練することで、「その時」に備えられたらいいなぁというのが、私たちの願いです。
防災ピクニック、こうして初回は無事に終えることができました。(ちょこっとやり残したこともありますが…笑)
参加してくれた皆さん、ありがとうございました!
当日、その後はもちろん、一同 川遊びへ直行でした(笑)
当日の様子について、参加してくれた、はっちゃんがブログにアップしてくれています。
お子さんの様子など、詳しく書いてくれています。
http://minkara.carview.co.jp/userid/2430953/blog/36187638/
さて。次回は冬場にも防災ピクニックをやってみたい!という声が上がりました。
今度は寒さから身を守る方法などなど、みんなでシェアしてみたいです。
もしご興味ある方は、ぜひご一緒に~。
tasuki防災部 部員募集中です!
https://www.facebook.com/groups/385781728274921/
※ゆるゆるやってます(笑)
モミコ
子どもたちが夏休みに入り、フル稼働なママも多いのではないでしょうか(笑)毎日お疲れ様ですm(__)m
さて、tasukiでは8/3(月)に防災部で参加者を集ってピクニックをしましたよ。
その名も「防災ピクニック」!

昨年より「ママのための防災講座」を定期開催しているtasuki。
いろいろと勉強する中で、野外のアウトドア経験が防災力アップにつながるなー!ということを感じていました。
そんなわけで、この夏休みの機会に、子どもたちと一緒にお試しで防災ピクニックをしてみよう!というのがきっかけです。
いやー。当日は暑かったけれど、楽しかったです!!
大人は8名。子どもは1歳から8歳の17名。合計25名が集まりました。
場所は長泉町にある『桃沢野外活動センター』。敷地内には桃沢川が流れ、川遊びの誘惑にチラチラひかれつつ(笑)、ピクニック開始です!
カマドに火を起こしたり。
男の子達が火の番人を自ら引き受けてくれました。頼もしい!
ハイゼックス炊飯袋を使って、お米を炊いたり。

白米の他、変わり種ご飯も炊いてみました!
(トマトジュースでリゾット風、塩昆布、コーン缶とツナ缶とコンソメでピラフ風など)
※ハイゼックス炊飯袋とは、災害時に最小限の材料で炊き出しできる魔法の炊飯袋と言われています。保存期間が長く、持ち運びに便利。袋から直接食べることもできるので、食器や箸が不要なのが特徴。大鍋で一度に何袋も炊き出しするのに便利な防災グッズ。
そうそう。参加してくれた子の中には、あらかじめ、おうちでピラフのレシピを書いて持ってきてくれた子もいました。優秀~!!
ついでに、おかずもハイゼックス炊飯袋で調理してみたり。


今回は、自宅にある缶詰を持ち寄って、それらと当日刻んだ人参・玉ねぎ・じゃがいもを組み合わせて何種類かのおかずを作ってみました。
この日は鶏ジャガや、ミネストローネ、王道のカレーなどを作りましたよ。
そうして袋ごと鍋に投入!

30分くらいグツグツしたら、出来上がり!

見た目はちょっとアレですが^^;
なんとかできあがりました!
火にかける時間が足りなくて、芯のあるご飯になってしまったものもありましたが、そんな芯飯を物ともせず、子どもたちはパクパクパクパク…
野外で食べる特別感が、そうさせるのでしょうか(@_@)
とにかく、多少、芯があっても結構イケル!ということが実証されました(笑)
またもう一つ、実証されたことが。
それは、
「カレーは万能!」
ということです。カレーが出てきた途端、子どもたちの食欲は倍増!ママ達も、その安心感に「やっぱりカレーは必須だね」と一同納得でした。
こういった野外のお楽しみイベントでさえ、そうなのだから、災害時は特に、食べなれたものを口にすると、安心感が増すよねーという話も出たりしました。
さて。
食後はちょっとしたお楽しみも用意しましたよ。
その名も「防災スタンプラリー」です。
内容は、
子どもたち一人ひとりにカードを配り、自分の身元情報(名前・年齢・住んでいる場所など、年齢に応じて項目を決めました)を参加者の大人に伝え、正確に伝えられたら、一人につき一つのサインをもらう。順次大人を回って、スタンプを集めたら景品(お菓子)と交換!というものです。

災害時、両親と離れてしまったとしても、こうして自分のことを近くにいる大人に伝えることができたら、いち早くお父さん・お母さんと再会できるきっかけになることは言うまでもありません。
子どもたちにとっては、この日初めて会う大人もいる中、また慣れないこともあって、最初はモジモジしてしまう場面もありました。
でも、お兄さん・お姉さんの姿に触発されて、頑張って伝える子どもたちの姿も見られて、良かったです☆
その他、「大声を出してみよう」「ホイッスルを吹いてみよう」ということで、野外で思いっきり声をだし、ホイッスルを吹いてみたりして、助けを呼ぶ練習もみんなでしてみました。
なかなかおうちではできないことですが、野外でみんなと、まずはやってみよう!と。
ホイッスルは、空気を出す穴をおさえてしまって、うまく音が出せなかったりする子もいました。
やはり、試してみないとわかりませんね~。
ほかにも、防災グッズの中で、持ってはいるけれど、使ったことがない!というものも、使ってみないと分からない使用感など、きっとありそうですね。。。
とにもかくにも、こうして楽しみながら訓練することで、「その時」に備えられたらいいなぁというのが、私たちの願いです。
防災ピクニック、こうして初回は無事に終えることができました。(ちょこっとやり残したこともありますが…笑)
参加してくれた皆さん、ありがとうございました!
当日、その後はもちろん、一同 川遊びへ直行でした(笑)
当日の様子について、参加してくれた、はっちゃんがブログにアップしてくれています。
お子さんの様子など、詳しく書いてくれています。
http://minkara.carview.co.jp/userid/2430953/blog/36187638/
さて。次回は冬場にも防災ピクニックをやってみたい!という声が上がりました。
今度は寒さから身を守る方法などなど、みんなでシェアしてみたいです。
もしご興味ある方は、ぜひご一緒に~。
tasuki防災部 部員募集中です!
https://www.facebook.com/groups/385781728274921/
※ゆるゆるやってます(笑)
モミコ
2015年06月26日
第1回ママのための防災講座 開催報告②
前回記事「第1回ママのための防災講座開催報告①」の続きです。

前回の記事では、「災害が起きたら、避難所へGO!」
という認識を改めましょうねー、
自宅で避難生活が送れるようにしましょうねー、
そのために必要なポイントは4つありますよー、という内容の講義をレポートしました。
ちなみにその4つのポイントはこちら。
しつこいくらいに繰り返します(笑)
①安全な家と部屋
②備蓄
③ママバッグ
④公助と共助を理解
そして、今回の講座では①の安全な家と部屋を確保するために必要な事を学んで、おうちに持ち帰り、実践に移して頂くことが私たちの願いなのでした。
では、安全な家と部屋を確保するために必要なポイントは??
講師の高良さんに説明していただきました。
☆優先順位をつける
お家の中、全ての部屋に対策を施せればベストですが、まずは優先的に、
「いつも子供が過ごす部屋」「寝室」から対策を。
☆家具への対策
→固定具として一つのアイテムだけでなく、
複数アイテムを組み合わせるとより安全!
例)TVの場合…耐震ジェル+固定ベルト(ワイヤー)/冷蔵庫の場合…突っ張り棒+天井にネジ打ち など
→家具の中身として、上は軽いものを 下は重いものを配置
→家具の角にはクッション材を
☆ガラスへの対策
→飛散防止のフィルムを貼る・固定する
☆避難経路を確保
→余計なものを置かない・ライトを常備
と、ポイントを押さえたところで、家庭内DIGのワークへ移りました。
DIGって、そもそも何!?という方は、昨年の記事(記事はこちら→☆)をご覧ください。
今回の家庭内DIG 当日のワークの流れは、
①自宅の平面図(見取り図)を書いてみよう!
細かく書いているとキリがありません(笑)ササッと5分くらいで皆さん書きあげていただきました。

図面持参で受講して下さった参加者も!その真剣さが嬉しかったです!!
②自宅の危険な場所をチェック!
・対策がとられているもの・危険ではないと判断出来るところには 『〇』
・少々不安が残るところには 『△』
・対策をとっておらず危険だと思われるところには 『×』

③グループごとに、判定内容や対応策について話し合おう!
困っている箇所や、具体的にどう対策したらよいか、また今後こうしたいと思う!などの意見を聞き合いました。

④全体でシェア(意見交換・情報交換)
グループ内で話した内容、対応策などを、各グループのtasukiスタッフがまとめて、みんなに発表しました。
各自→グループ→全体 とシェアすることにより、自分が気が付かなかったところを再認識することや違った見方をすることができました。

全体でシェアした内容(質問については、講師からの回答)はこちら↓↓↓
【家具・収納のスマート化について】
・寝室に背の高い家具が集中している
→別の場所への移動を考えたい&ものを減らしたい
・家具の下の方に重いもの・上の方に軽いものをと思っても、重くて割れる危険のあるものなどは、子どもの手の届かない上部へ置きがち。
→本当にそこにないといけないものかどうか選別し、割れる危険のあるものを安全に収納できるスペースを確保する
・(新築の方)収納をたくさん作ることで、床置きの家具をほとんどなくした
【TVの固定について】
・TVの背面が壁ではなく、窓だった場合はどうしたらいいか?
→TV台と床を固定&TV台とTVをジェルなどで固定した上で、倒れても画面が割れないようにカバーをつける
【窓ガラスへの対策について】
・全ての部屋にフィルムを貼るのは、お金がかかりそう。
→優先的にリビングと子どもの部屋から
・(新築の方)窓ガラスに飛散防止フィルムを貼らず、強度の強いガラスを知り、採用した
【ダイニングテーブルの固定について】
・固定していなくて心配。対策としては、耐震ジェルでよいか?
→動いて挟まれたら、身動きがとれなくなりそうなテーブルについては、ジェルでの固定がベター。
【その他】
・賃貸暮らしなので、壁や天井に穴を開けて家具を固定するのは気が引ける。かと言って、突っ張り棒だけでの固定だと不安。
→対策は命に関わること。何を優先するかは個々で判断するしかない。
突っ張り棒だけで不安な箇所は、+ねじ打ちなど、合わせ技での固定がベター。
・同居の親の部屋が心配
→優先的にリビングと子どもの部屋から対策を
・建具の観音開きの棚について、地震の際に扉が開いてしまいそうなので、S字フックを取っ手につけた
・エアコンがどのように壁につけてあるのか?また、どんな対策が必要なのか??
→講師・高良さんへの宿題ということになりました。
当日の講座は、この後、質疑応答があり、終了しました。
内容としてはここまでですが、受講生の皆さんは、ここで終わってはいけません。
大切なのは、何より、この後のアクション!!!
グループワークの際、受講生の皆さんへの宿題として、3つのアクションを書きだして頂きました。
おうちに帰って、何かしらの行動・対策につなげて頂きたい!という願いからです。
受講生の皆さーん、その後どうですか??
そんな情報交換の場になればいいなということで、Facebookグループに「tasuki防災部」を立ち上げ、受講生の皆さん(facebookにアカウントを持っている方)を招待させていただきました。こちらで防災に関する情報交換をしていきたいと思っています!
(かなりユルーい部活です・笑)
https://www.facebook.com/groups/385781728274921/
公開グループになっていますので、ご興味ある方はぜひ!一緒に情報交換しましょー。
さて、
今回の講座は、スタッフにとっては昨年に引き続き2度目。内容はじゅうぶん理解しているつもりでいましたが、またこうして高良さんのお話しを聞いたり、皆さんと情報をシェアする中で、対策の足りないところをなんとかせねば!と、またグンと士気が高まりました。
熱の冷めないうちに、取り組みたいと思います!
自分の家族を守りたい!その思いで行動を起こし、対策を積み重ねて「我が家は大丈夫!」と言えるようになれば、本当に助けが必要な人の命を救うことにつながる。
もう、やらないわけにはいきませんね・笑
最後になりましたが、今回の講座開催にあたり、講師の高良綾乃さま、託児ボランティアの皆さま、第一建設株式会社沼津支店さま、亀田製菓株式会社さまにご協力いただきました。ありがとうございましたm(__)m
次回の講座は9月に開催予定です。テーマは「無理なくできる!日ごろからの備蓄」です。
また詳細が決まり次第、このブログでお知らせいたしますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(モミコ)

前回の記事では、「災害が起きたら、避難所へGO!」
という認識を改めましょうねー、
自宅で避難生活が送れるようにしましょうねー、
そのために必要なポイントは4つありますよー、という内容の講義をレポートしました。
ちなみにその4つのポイントはこちら。
しつこいくらいに繰り返します(笑)
①安全な家と部屋
②備蓄
③ママバッグ
④公助と共助を理解
そして、今回の講座では①の安全な家と部屋を確保するために必要な事を学んで、おうちに持ち帰り、実践に移して頂くことが私たちの願いなのでした。
では、安全な家と部屋を確保するために必要なポイントは??
講師の高良さんに説明していただきました。
☆優先順位をつける
お家の中、全ての部屋に対策を施せればベストですが、まずは優先的に、
「いつも子供が過ごす部屋」「寝室」から対策を。
☆家具への対策
→固定具として一つのアイテムだけでなく、
複数アイテムを組み合わせるとより安全!
例)TVの場合…耐震ジェル+固定ベルト(ワイヤー)/冷蔵庫の場合…突っ張り棒+天井にネジ打ち など
→家具の中身として、上は軽いものを 下は重いものを配置
→家具の角にはクッション材を
☆ガラスへの対策
→飛散防止のフィルムを貼る・固定する
☆避難経路を確保
→余計なものを置かない・ライトを常備
と、ポイントを押さえたところで、家庭内DIGのワークへ移りました。
DIGって、そもそも何!?という方は、昨年の記事(記事はこちら→☆)をご覧ください。
今回の家庭内DIG 当日のワークの流れは、
①自宅の平面図(見取り図)を書いてみよう!
細かく書いているとキリがありません(笑)ササッと5分くらいで皆さん書きあげていただきました。

②自宅の危険な場所をチェック!
・対策がとられているもの・危険ではないと判断出来るところには 『〇』
・少々不安が残るところには 『△』
・対策をとっておらず危険だと思われるところには 『×』

③グループごとに、判定内容や対応策について話し合おう!
困っている箇所や、具体的にどう対策したらよいか、また今後こうしたいと思う!などの意見を聞き合いました。

④全体でシェア(意見交換・情報交換)
グループ内で話した内容、対応策などを、各グループのtasukiスタッフがまとめて、みんなに発表しました。
各自→グループ→全体 とシェアすることにより、自分が気が付かなかったところを再認識することや違った見方をすることができました。

全体でシェアした内容(質問については、講師からの回答)はこちら↓↓↓
【家具・収納のスマート化について】
・寝室に背の高い家具が集中している
→別の場所への移動を考えたい&ものを減らしたい
・家具の下の方に重いもの・上の方に軽いものをと思っても、重くて割れる危険のあるものなどは、子どもの手の届かない上部へ置きがち。
→本当にそこにないといけないものかどうか選別し、割れる危険のあるものを安全に収納できるスペースを確保する
・(新築の方)収納をたくさん作ることで、床置きの家具をほとんどなくした
【TVの固定について】
・TVの背面が壁ではなく、窓だった場合はどうしたらいいか?
→TV台と床を固定&TV台とTVをジェルなどで固定した上で、倒れても画面が割れないようにカバーをつける
【窓ガラスへの対策について】
・全ての部屋にフィルムを貼るのは、お金がかかりそう。
→優先的にリビングと子どもの部屋から
・(新築の方)窓ガラスに飛散防止フィルムを貼らず、強度の強いガラスを知り、採用した
【ダイニングテーブルの固定について】
・固定していなくて心配。対策としては、耐震ジェルでよいか?
→動いて挟まれたら、身動きがとれなくなりそうなテーブルについては、ジェルでの固定がベター。
【その他】
・賃貸暮らしなので、壁や天井に穴を開けて家具を固定するのは気が引ける。かと言って、突っ張り棒だけでの固定だと不安。
→対策は命に関わること。何を優先するかは個々で判断するしかない。
突っ張り棒だけで不安な箇所は、+ねじ打ちなど、合わせ技での固定がベター。
・同居の親の部屋が心配
→優先的にリビングと子どもの部屋から対策を
・建具の観音開きの棚について、地震の際に扉が開いてしまいそうなので、S字フックを取っ手につけた
・エアコンがどのように壁につけてあるのか?また、どんな対策が必要なのか??
→講師・高良さんへの宿題ということになりました。
当日の講座は、この後、質疑応答があり、終了しました。
内容としてはここまでですが、受講生の皆さんは、ここで終わってはいけません。
大切なのは、何より、この後のアクション!!!
グループワークの際、受講生の皆さんへの宿題として、3つのアクションを書きだして頂きました。
おうちに帰って、何かしらの行動・対策につなげて頂きたい!という願いからです。
受講生の皆さーん、その後どうですか??
そんな情報交換の場になればいいなということで、Facebookグループに「tasuki防災部」を立ち上げ、受講生の皆さん(facebookにアカウントを持っている方)を招待させていただきました。こちらで防災に関する情報交換をしていきたいと思っています!
(かなりユルーい部活です・笑)
https://www.facebook.com/groups/385781728274921/
公開グループになっていますので、ご興味ある方はぜひ!一緒に情報交換しましょー。
さて、
今回の講座は、スタッフにとっては昨年に引き続き2度目。内容はじゅうぶん理解しているつもりでいましたが、またこうして高良さんのお話しを聞いたり、皆さんと情報をシェアする中で、対策の足りないところをなんとかせねば!と、またグンと士気が高まりました。
熱の冷めないうちに、取り組みたいと思います!
自分の家族を守りたい!その思いで行動を起こし、対策を積み重ねて「我が家は大丈夫!」と言えるようになれば、本当に助けが必要な人の命を救うことにつながる。
もう、やらないわけにはいきませんね・笑
最後になりましたが、今回の講座開催にあたり、講師の高良綾乃さま、託児ボランティアの皆さま、第一建設株式会社沼津支店さま、亀田製菓株式会社さまにご協力いただきました。ありがとうございましたm(__)m
次回の講座は9月に開催予定です。テーマは「無理なくできる!日ごろからの備蓄」です。
また詳細が決まり次第、このブログでお知らせいたしますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(モミコ)
2015年06月24日
第1回ママのための防災講座 開催報告①
6/20(土)にママのための防災講座を開催しました!
昨年4回シリーズで開催した本講座。好評につきリピート開催した、その第1回目の講座なのでした!
今回、土曜開催を試みてみたものの、参加者が集まるか心配していましたが、
見学に見えた方も含めて、合計18名の方に受講いただきました。
受講頂いた皆様、お子さんを連れての受講は大変な面もあったかと思います。貴重な土曜日の時間をこの講座に割いていただき、ありがとうございました!

講師はおなじみ!沼津市災害ボランティアコーディネーター協会の高良綾乃さんです。
最近、ママ向けの防災講座の講師としてあちこち引っ張りダコの高良さん♪
「防災」というと、どこから手をつけていいか分からなくなりがちですが、色々な情報がある中で、ママ達が何を優先して、どこにポイントに置いて対策したらいいのか、いつもスッキリ整理して伝えてくださいます。tasukiは本当に素晴らしい講師に恵まれています\(^o^)/
少し脱線しますが、、、高良さんは、本業でお弁当講師をされています。
気になる方は、こちらのブログをチェック!(http://ameblo.jp/vege-takarabako/)たまに防災ネタもアップされるので、要チェックブログですよー(*^_^*)
さて、講師へのゴマスリはここまでにして本題に戻りまして・笑
今回の講座のテーマは「子どもを守る部屋づくり」。
こんな流れで進んで行きましたよー。
☆避難所ってどんなとこ?
☆避難所のメリット・デメリット
☆自宅での避難生活に必要なこと
☆安全な家と部屋のポイント
☆【ワーク】家庭内DIG
それぞれ、振り返ってみますね。
☆避難所ってどんなとこ?
「大地震が来たら、とりあえず避難所へ行けばいいや!
そう考えていませんか??」
という高良さんの問いかけに、参加者もうなずき気味……。
そこで、避難所の現状をおさえるところから。
沼津市を例に挙げ、沼津市民がみーんなそれぞれ避難所に駆け込んだらどうなるかを説明していただきました。
沼津市の人口は約20万人。そして、沼津市内の避難所の数は約50箇所。
なんとっ!1か所の避難所に約4000人の割り当てになる計算なのです!!!
せいぜい、避難所には収容できて200人が限度。なので、ほとんどの方が入れない!という訳なのです。こ、これは大変!!
そして、避難所には、優先的に入るべき人がいると。
具体的に優先されるのは、「ケアが必要な人」「避難勧告の出た人」「家の倒壊で生活困難な人」になると。
単に乳幼児がいる!というだけでは、特別扱いはされないと思っておいた方が良さそうです。
というわけで結論!
「避難所は、あくまでも自力・自宅で生活することが困難な方がやむを得ず一時的に身を寄せる場所」
むむー。一同、納得でした。

会場内のスペースで遊ぶ子ども達……賑やかでした・笑
ではでは、避難所ってほんとに行かない方がいいの?行かないと支援物資がもらえないんじゃないの?
行かないと損なのでは…そんな疑問については、次のテーマで話していただきました。
☆避難所のメリットデメリット
【メリット】は、、、
①ケアの必要な人にとっては、周りに人の目があり、人の手があることで安心
②出産時期の近いママなど、一人でいることに不安を感じる人にとっては安心
③情報が入ってきやすい など
反対に
【デメリット】は、、、
①感染症の危険(衛生状態が良くないため)
②避難所運営スタッフとしての役割(子連れで、その役割が担えるかどうか疑問)
③お子さんの騒音問題(肩身の狭い思いをすることは間違いない)
④犯罪の危険 など
デメリットを聞いていると、会場は段々とドンヨリとした空気に…笑
特に④の犯罪については、なかなか報道として取り上げられにくい問題で、表には出てきていませんが、東日本大震災の際にも多数あったとのこと。講座では、具体的な事例を話していただきました。
その話を聞いて、ますます会場はドンヨリ。。。
でも、「知る」って大切ですね。そんな避難所の現状を知ることで、わざわざ大切な子どもを避難所に連れて行くもんか!そんな気がしてきます。
(もちろん、真摯に避難所運営にあたっているスタッフの方々を否定するのではなく、あくまでも、その方々の手の届かないところで、いろんな問題が起こりうるということです。)
というわけで結論!
「小さなお子さんがいるご家庭は、自宅で避難生活を送るのがベター。」
避難所は、子連れではとても生活できる環境ではないので(衛生問題や、お子さんの騒音問題などなどから)、住み慣れた自宅で避難生活が送れるようにすることが、ママにとってもお子さんにとってもストレスの少ない選択になるということですね。
津波被害の危険性のある沿岸部にお住まいの方たちはこの限りでは有りませんが、確かに、避難所でしか得られない情報や物資があるとはいえ、「基本的な生活はおうちで」ということを念頭に置いた方が良さそうです。
さて、ではその自宅避難生活をするために、ポイントとなることは?
次のテーマで説明頂きました。
☆自宅での避難生活に必要なこと
①安全な家と部屋を確保すること……昭和56年以降に建てられた家/家具の固定
②最低限の備蓄をすること……ローリングストックとママバッグと車の対策
③ママバッグを防災仕様にすること……日ごろの用意をバッグと車に
④公助と共助を理解すること……公助と共助を把握して仏子糸情報をキャッチ
お気づきの方もいるかもしれませんが、本講座が4回シリーズになっているのは、この4つのポイントを一つずつテーマにして組み立てているからなのですっ!今回の第1回目の講座のテーマは、このポイントの内、「①安全な家と部屋を確保すること」。普段お子さんと長い時間を過ごす部屋を見直してみよう!ということで、受講生の皆さんと一緒に考え、どんな小さなことでもいいから、皆さんが実行に移せるようにと願って開催したものなのです。
そして、講座はグループワークへと移っていきます。
受講生の皆さんに、それぞれご自宅の間取り図を書いて頂き、話し合いの時間をもちました。

続きはまた次回アップします。
次回は、安全な家と部屋のポイントと、グループワークについて、レポートします!
モミコ
昨年4回シリーズで開催した本講座。好評につきリピート開催した、その第1回目の講座なのでした!
今回、土曜開催を試みてみたものの、参加者が集まるか心配していましたが、
見学に見えた方も含めて、合計18名の方に受講いただきました。
受講頂いた皆様、お子さんを連れての受講は大変な面もあったかと思います。貴重な土曜日の時間をこの講座に割いていただき、ありがとうございました!

講師はおなじみ!沼津市災害ボランティアコーディネーター協会の高良綾乃さんです。
最近、ママ向けの防災講座の講師としてあちこち引っ張りダコの高良さん♪
「防災」というと、どこから手をつけていいか分からなくなりがちですが、色々な情報がある中で、ママ達が何を優先して、どこにポイントに置いて対策したらいいのか、いつもスッキリ整理して伝えてくださいます。tasukiは本当に素晴らしい講師に恵まれています\(^o^)/
少し脱線しますが、、、高良さんは、本業でお弁当講師をされています。
気になる方は、こちらのブログをチェック!(http://ameblo.jp/vege-takarabako/)たまに防災ネタもアップされるので、要チェックブログですよー(*^_^*)
さて、
今回の講座のテーマは「子どもを守る部屋づくり」。
こんな流れで進んで行きましたよー。
☆避難所ってどんなとこ?
☆避難所のメリット・デメリット
☆自宅での避難生活に必要なこと
☆安全な家と部屋のポイント
☆【ワーク】家庭内DIG
それぞれ、振り返ってみますね。
☆避難所ってどんなとこ?
「大地震が来たら、とりあえず避難所へ行けばいいや!
そう考えていませんか??」
という高良さんの問いかけに、参加者もうなずき気味……。
そこで、避難所の現状をおさえるところから。
沼津市を例に挙げ、沼津市民がみーんなそれぞれ避難所に駆け込んだらどうなるかを説明していただきました。
沼津市の人口は約20万人。そして、沼津市内の避難所の数は約50箇所。
なんとっ!1か所の避難所に約4000人の割り当てになる計算なのです!!!
せいぜい、避難所には収容できて200人が限度。なので、ほとんどの方が入れない!という訳なのです。こ、これは大変!!
そして、避難所には、優先的に入るべき人がいると。
具体的に優先されるのは、「ケアが必要な人」「避難勧告の出た人」「家の倒壊で生活困難な人」になると。
単に乳幼児がいる!というだけでは、特別扱いはされないと思っておいた方が良さそうです。
というわけで結論!
「避難所は、あくまでも自力・自宅で生活することが困難な方がやむを得ず一時的に身を寄せる場所」
むむー。一同、納得でした。

ではでは、避難所ってほんとに行かない方がいいの?行かないと支援物資がもらえないんじゃないの?
行かないと損なのでは…そんな疑問については、次のテーマで話していただきました。
☆避難所のメリットデメリット
【メリット】は、、、
①ケアの必要な人にとっては、周りに人の目があり、人の手があることで安心
②出産時期の近いママなど、一人でいることに不安を感じる人にとっては安心
③情報が入ってきやすい など
反対に
【デメリット】は、、、
①感染症の危険(衛生状態が良くないため)
②避難所運営スタッフとしての役割(子連れで、その役割が担えるかどうか疑問)
③お子さんの騒音問題(肩身の狭い思いをすることは間違いない)
④犯罪の危険 など
デメリットを聞いていると、会場は段々とドンヨリとした空気に…笑
特に④の犯罪については、なかなか報道として取り上げられにくい問題で、表には出てきていませんが、東日本大震災の際にも多数あったとのこと。講座では、具体的な事例を話していただきました。
その話を聞いて、ますます会場はドンヨリ。。。
でも、「知る」って大切ですね。そんな避難所の現状を知ることで、わざわざ大切な子どもを避難所に連れて行くもんか!そんな気がしてきます。
(もちろん、真摯に避難所運営にあたっているスタッフの方々を否定するのではなく、あくまでも、その方々の手の届かないところで、いろんな問題が起こりうるということです。)
というわけで結論!
「小さなお子さんがいるご家庭は、自宅で避難生活を送るのがベター。」
避難所は、子連れではとても生活できる環境ではないので(衛生問題や、お子さんの騒音問題などなどから)、住み慣れた自宅で避難生活が送れるようにすることが、ママにとってもお子さんにとってもストレスの少ない選択になるということですね。
津波被害の危険性のある沿岸部にお住まいの方たちはこの限りでは有りませんが、確かに、避難所でしか得られない情報や物資があるとはいえ、「基本的な生活はおうちで」ということを念頭に置いた方が良さそうです。
さて、ではその自宅避難生活をするために、ポイントとなることは?
次のテーマで説明頂きました。
☆自宅での避難生活に必要なこと
①安全な家と部屋を確保すること……昭和56年以降に建てられた家/家具の固定
②最低限の備蓄をすること……ローリングストックとママバッグと車の対策
③ママバッグを防災仕様にすること……日ごろの用意をバッグと車に
④公助と共助を理解すること……公助と共助を把握して仏子糸情報をキャッチ
お気づきの方もいるかもしれませんが、本講座が4回シリーズになっているのは、この4つのポイントを一つずつテーマにして組み立てているからなのですっ!今回の第1回目の講座のテーマは、このポイントの内、「①安全な家と部屋を確保すること」。普段お子さんと長い時間を過ごす部屋を見直してみよう!ということで、受講生の皆さんと一緒に考え、どんな小さなことでもいいから、皆さんが実行に移せるようにと願って開催したものなのです。
そして、講座はグループワークへと移っていきます。
受講生の皆さんに、それぞれご自宅の間取り図を書いて頂き、話し合いの時間をもちました。

続きはまた次回アップします。
次回は、安全な家と部屋のポイントと、グループワークについて、レポートします!
モミコ
2015年06月04日
第一回 ママのための防災講座 参加者募集!
すっかりご無沙汰しております・・・
入園入学進級で慌ただしい4月5月が過ぎ、もう6月に突入!
ポケーっとしている間に月日はどんどん過ぎて行き、若干、いえ、かなり焦っております(苦笑)
さて、今日はtasuki主催『ママのための防災講座』の参加者募集のお知らせです。
昨年度、大好評だったこちらの全4回の講座をまた3月までに4回に渡り、開催いたします。
その第1回目の講座について、参加者を大募集いたします!
今回のテーマは「子どもを守る部屋づくり」。
自宅で避難できるよう、その心構えから、家庭内DIGの実習、そしてアクションのポイントを盛り込んだ、充実した内容です。
今回は初の土曜開催♪パパさんも、ぜひご一緒にご参加ください!

『第1回ママのための防災講座 with tasuki ~子どもを守る部屋づくり 』
【主催】子育て応援サークルtasuki
【日時】平成27年6月20日(土)10:00~11:30
【場所】門池地区センター2階小会議室
【対象】子育て中の親御さん 20組
【託児】5名(0歳~2歳11カ月)※3歳以上のお子様は同席をお願いします。
【受講料】500円(1家族につき)
【託児料】300円
※希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※受講できない方には6/15以降にご連絡いたします。
連絡のない方は受講可能です。
※申し込みを取り消し・キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。
【内容】
・避難所の現実を知ろう!
・自宅避難を目指そう!
・家庭内dig
・防災・減災グッズの紹介 など
【申込み・問合せ】子育て応援サークルtasuki
下記メールアドレス宛に、①~④の内容を明記の上、お申し込みください。
①保護者氏名(ご夫婦で参加される場合はご夫婦ともご記入ください)
②住所・電話番号③託児希望(有・無)
④託児希望の場合、お子さんのお名前(ひらがな)・年齢(○歳○ヶ月)
MAIL:staff.tasuki☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
この防災講座は、「なかなか意識を継続することが難しいけれども、小さなお子さんを抱えるママにとっては、子どもと家族を守るために大切なこと……防災。一人では難しいけれど、一緒に楽しく学ぼう!行動に起こそう!そして、地震に強いママになろう!」そんな願いを持って、数回に分けて企画している、tasukiオリジナル講座です。
今回は全4回シリーズの初回。第1回から第3回までは自助(自らと家族の命は自らが守ること・備えること)がテーマです。第4回は共助(近隣が助け合って地域を守ること・備えること)と公助(公的機関や企業による応急・復旧対策活動)がテーマです。いつからでも、何回でも参加OK!
今後の予定は、このようになっています↓
【第2回】無理なくできる!日ごろからの備蓄(9月開催予定)
【第3回】ママバッグを防災仕様に!(12月開催予定)
【第4回】公助と共助~学ぼう助け合いのココロ~(3月開催予定)
講師には、tasukiの強力な防災パートナーである高良綾乃さん(沼津市災害ボランティアコーディネーター協会所属)が全面的に協力してくださっています。
高良さんのお話は、いつも整理されていて、具体的で前向き!スタッフはいつもハッとさせられ、いい刺激を頂いています。
☆講師 高良さんのブログ http://blogs.yahoo.co.jp/ayaraccho
今まで受講された方も、受講されなかった方も、いつからでもご一緒に、私たちと防災を楽しく学んでみませんか?
皆さまからのご応募をお待ちしております!
入園入学進級で慌ただしい4月5月が過ぎ、もう6月に突入!
ポケーっとしている間に月日はどんどん過ぎて行き、若干、いえ、かなり焦っております(苦笑)
さて、今日はtasuki主催『ママのための防災講座』の参加者募集のお知らせです。
昨年度、大好評だったこちらの全4回の講座をまた3月までに4回に渡り、開催いたします。
その第1回目の講座について、参加者を大募集いたします!
今回のテーマは「子どもを守る部屋づくり」。
自宅で避難できるよう、その心構えから、家庭内DIGの実習、そしてアクションのポイントを盛り込んだ、充実した内容です。
今回は初の土曜開催♪パパさんも、ぜひご一緒にご参加ください!

『第1回ママのための防災講座 with tasuki ~子どもを守る部屋づくり 』
【主催】子育て応援サークルtasuki
【日時】平成27年6月20日(土)10:00~11:30
【場所】門池地区センター2階小会議室
【対象】子育て中の親御さん 20組
【託児】5名(0歳~2歳11カ月)※3歳以上のお子様は同席をお願いします。
【受講料】500円(1家族につき)
【託児料】300円
※希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※受講できない方には6/15以降にご連絡いたします。
連絡のない方は受講可能です。
※申し込みを取り消し・キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。
【内容】
・避難所の現実を知ろう!
・自宅避難を目指そう!
・家庭内dig
・防災・減災グッズの紹介 など
【申込み・問合せ】子育て応援サークルtasuki
下記メールアドレス宛に、①~④の内容を明記の上、お申し込みください。
①保護者氏名(ご夫婦で参加される場合はご夫婦ともご記入ください)
②住所・電話番号③託児希望(有・無)
④託児希望の場合、お子さんのお名前(ひらがな)・年齢(○歳○ヶ月)
MAIL:staff.tasuki☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
この防災講座は、「なかなか意識を継続することが難しいけれども、小さなお子さんを抱えるママにとっては、子どもと家族を守るために大切なこと……防災。一人では難しいけれど、一緒に楽しく学ぼう!行動に起こそう!そして、地震に強いママになろう!」そんな願いを持って、数回に分けて企画している、tasukiオリジナル講座です。
今回は全4回シリーズの初回。第1回から第3回までは自助(自らと家族の命は自らが守ること・備えること)がテーマです。第4回は共助(近隣が助け合って地域を守ること・備えること)と公助(公的機関や企業による応急・復旧対策活動)がテーマです。いつからでも、何回でも参加OK!
今後の予定は、このようになっています↓
【第2回】無理なくできる!日ごろからの備蓄(9月開催予定)
【第3回】ママバッグを防災仕様に!(12月開催予定)
【第4回】公助と共助~学ぼう助け合いのココロ~(3月開催予定)
講師には、tasukiの強力な防災パートナーである高良綾乃さん(沼津市災害ボランティアコーディネーター協会所属)が全面的に協力してくださっています。
高良さんのお話は、いつも整理されていて、具体的で前向き!スタッフはいつもハッとさせられ、いい刺激を頂いています。
☆講師 高良さんのブログ http://blogs.yahoo.co.jp/ayaraccho
今まで受講された方も、受講されなかった方も、いつからでもご一緒に、私たちと防災を楽しく学んでみませんか?
皆さまからのご応募をお待ちしております!
2015年03月18日
第4回ママのための防災講座 開催報告②
3/13(金)に行われた「第4回ママのための防災講座」開催報告その2です。
(開催報告その1はこちら→☆)

講座前半では、沼津市災害ボランティアコーディネーター協会の高良さんより、「公助って?」という話の中で、公助の限界を認識しました。
また、「公助」と「自助」をつなぐのが「共助」だというお話も。そこで、私達も共助の一員!ということがわかり、シチュエーション別に行動に移せることを確認しました。
しかし、私達、乳幼児のママは、いざという時、子どもを抱えて、そんなにたくさんのことはできません
そこでお次の話題は、「子連れでできる共助って?」でした。
子連れでできる共助……それは、「声」だそうです
・「火事だー!!」「人が倒れています!」「誰か手伝ってください!」という発災直後の声掛け。
・「大丈夫ですか?」「また来ますね」「何かあればお互い声掛けしましょう」というご近所同士の声掛け。
うんうん。これなら、乳飲み子を抱えていても、できそうですよね
そして、ご近所づきあいは、日ごろからの関わり方次第で、きっと災害時に活きてきますよね。更に高良さんから、「ご近所にママ友がいると、お互いに助け合えるし、安心度がぐっと上がる。」とも。
これには、会場一同、納得でした。遠くのママ友もいいですが、いざという時は、境遇を分かち合えるご近所のママ友と助け合い、その時を一緒に乗り越えられたらいいですね。もちろん、ママだけで固まるのではなく、世代を超えて、ご近所で分かち合う&助け合うココロも持っていたいですね
また、災害時に自分や周りに怪我をした人がいた際に、どう行動したらいいか?というお話しもありました。
病院ではなく、「歩ける人は原則、救護所へ行くか自宅待機」。
怪我する我が子を、ただ待たせるなんて ……と、実際に想像すると痛ましいですが、そうすることで、本当に治療・処置を急ぐ人に適切な医療行為ができるんだ!ということで、一同、激しく納得しました
……と、実際に想像すると痛ましいですが、そうすることで、本当に治療・処置を急ぐ人に適切な医療行為ができるんだ!ということで、一同、激しく納得しました
と同時に、「応急手当の知識を身につけたいと思った」という参加者も多数いたようです。スバラシイ
そして、高良さんが所属されている災害ボランティアの活動についてもお話がありました。災害ボランティアの方たちが、どうやって現地に入ってくるのか、その登録のしくみと派遣までの流れ、できること・できないこと、また注意すべき点について。その話を聞いて、ボランティアの方たちに、ますます頭が下がる思いがしました
これらのことを知っておくと、いざという時にも冷静に適切に対応ができるように思います。
講座では、この他、オブザーバーとして参加いただいたの元防災士の村木さんに、地域の消防団のお話をしていただいたり、「災害用伝言板web171」の体験利用をして終了しました。
※web171は毎月1日と15日に体験利用ができます。ぜひご家族・友人と一度お試しください
https://www.web171.jp/web171app/topRedirect.do


最後に、「『人に助けてもらう方法』ではなく、『自分を守り、人と助け合う方法』を学ぶのが防災です!」という、高良さんの言葉が胸に染みました。そして、今回の「共助」・「公助」を学んだことで、ますます「自助」の大切さを実感しています。
そうそう
「自助」と言えば、昨年のtasukiの防災講座(1回目~3回目)では、「自助」について学べる内容で開催しました。
今回の4回目までと同じ内容で、また5月以降、tasukiでは防災講座を継続開催していく予定です
全4回のテーマはこちらです↓↓↓
①子どもを守る部屋づくり
②無理なくできる!日ごろからの備蓄
③ママバックを防災仕様に!
④共助と公助・学ぼう助け合いのココロ
引き続き、共助の第一歩とも言える、「自助」、そして助け合いのココロで自分にできることを広げ・深めていく「共助」を皆さんと学び、行動に移していけたらと思っています。これまで開催した4回の講座の反省点を活かして、更にみなさんのお役に立てる防災講座を来年度も開催していきたいと思います
詳細決まりましたら、またこのブログでも告知させていただきますね。お楽しみに
今回の講座開催にあたり、講師の高良綾乃さま、託児ボランティアの皆さま、沼子連の村木豊さま、第一建設株式会社沼津支店さま、亀田製菓株式会社さま、☆☆Candy-box☆☆渡辺末美さま、Hawaian Relaxation LEHUAさまに、様々なかたちでご協力いただきました。ありがとうございましたm(__)m
長々とした報告になってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(開催報告その1はこちら→☆)

講座前半では、沼津市災害ボランティアコーディネーター協会の高良さんより、「公助って?」という話の中で、公助の限界を認識しました。
また、「公助」と「自助」をつなぐのが「共助」だというお話も。そこで、私達も共助の一員!ということがわかり、シチュエーション別に行動に移せることを確認しました。
しかし、私達、乳幼児のママは、いざという時、子どもを抱えて、そんなにたくさんのことはできません

そこでお次の話題は、「子連れでできる共助って?」でした。
子連れでできる共助……それは、「声」だそうです

・「火事だー!!」「人が倒れています!」「誰か手伝ってください!」という発災直後の声掛け。
・「大丈夫ですか?」「また来ますね」「何かあればお互い声掛けしましょう」というご近所同士の声掛け。
うんうん。これなら、乳飲み子を抱えていても、できそうですよね

そして、ご近所づきあいは、日ごろからの関わり方次第で、きっと災害時に活きてきますよね。更に高良さんから、「ご近所にママ友がいると、お互いに助け合えるし、安心度がぐっと上がる。」とも。
これには、会場一同、納得でした。遠くのママ友もいいですが、いざという時は、境遇を分かち合えるご近所のママ友と助け合い、その時を一緒に乗り越えられたらいいですね。もちろん、ママだけで固まるのではなく、世代を超えて、ご近所で分かち合う&助け合うココロも持っていたいですね

また、災害時に自分や周りに怪我をした人がいた際に、どう行動したらいいか?というお話しもありました。
病院ではなく、「歩ける人は原則、救護所へ行くか自宅待機」。
怪我する我が子を、ただ待たせるなんて
 ……と、実際に想像すると痛ましいですが、そうすることで、本当に治療・処置を急ぐ人に適切な医療行為ができるんだ!ということで、一同、激しく納得しました
……と、実際に想像すると痛ましいですが、そうすることで、本当に治療・処置を急ぐ人に適切な医療行為ができるんだ!ということで、一同、激しく納得しました
と同時に、「応急手当の知識を身につけたいと思った」という参加者も多数いたようです。スバラシイ

そして、高良さんが所属されている災害ボランティアの活動についてもお話がありました。災害ボランティアの方たちが、どうやって現地に入ってくるのか、その登録のしくみと派遣までの流れ、できること・できないこと、また注意すべき点について。その話を聞いて、ボランティアの方たちに、ますます頭が下がる思いがしました

これらのことを知っておくと、いざという時にも冷静に適切に対応ができるように思います。
講座では、この他、オブザーバーとして参加いただいたの元防災士の村木さんに、地域の消防団のお話をしていただいたり、「災害用伝言板web171」の体験利用をして終了しました。
※web171は毎月1日と15日に体験利用ができます。ぜひご家族・友人と一度お試しください

https://www.web171.jp/web171app/topRedirect.do


最後に、「『人に助けてもらう方法』ではなく、『自分を守り、人と助け合う方法』を学ぶのが防災です!」という、高良さんの言葉が胸に染みました。そして、今回の「共助」・「公助」を学んだことで、ますます「自助」の大切さを実感しています。
そうそう

「自助」と言えば、昨年のtasukiの防災講座(1回目~3回目)では、「自助」について学べる内容で開催しました。
今回の4回目までと同じ内容で、また5月以降、tasukiでは防災講座を継続開催していく予定です

全4回のテーマはこちらです↓↓↓
①子どもを守る部屋づくり
②無理なくできる!日ごろからの備蓄
③ママバックを防災仕様に!
④共助と公助・学ぼう助け合いのココロ
引き続き、共助の第一歩とも言える、「自助」、そして助け合いのココロで自分にできることを広げ・深めていく「共助」を皆さんと学び、行動に移していけたらと思っています。これまで開催した4回の講座の反省点を活かして、更にみなさんのお役に立てる防災講座を来年度も開催していきたいと思います

詳細決まりましたら、またこのブログでも告知させていただきますね。お楽しみに

今回の講座開催にあたり、講師の高良綾乃さま、託児ボランティアの皆さま、沼子連の村木豊さま、第一建設株式会社沼津支店さま、亀田製菓株式会社さま、☆☆Candy-box☆☆渡辺末美さま、Hawaian Relaxation LEHUAさまに、様々なかたちでご協力いただきました。ありがとうございましたm(__)m
長々とした報告になってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2015年03月17日
第4回ママのための防災講座 開催報告①
3/13(金)に『第4回ママのための防災講座』を開催しました!
1回目のテーマは『子どもを守る部屋づくり』、2回目は『無理なくできる!日ごろからの備蓄』、3回目は『ママバッグを防災仕様に』でした。これまでの3回は、自助がテーマ。そして今回は『共助と公助・学ぼう助け合いのココロ』と題して、公助って?共助って?というところから、私達自身にできる助け合いのココロを学ぶことがテーマでした。
今回も講師は沼津市災害ボランティアコーディネーター協会災害対策委員会の高良綾乃さん。(その絶妙の語り口に、高良さんファンがじわじわ増殖中!いつもありがとうございます )
)
講座は高良さんの講義からスタートです。
【1】公助について、もっと知ろう
公助とは何か、それを具体的にイメージできるようにお話いただきました。
主体は行政や消防になります。災害時の対応は、ライフラインの復旧や消火救援活動、また支援物資の配給などがあり、てんてこ舞い
つまり、災害時に役所や消防は、私達市民一人一人、「個人」への対応はムリ!ということが見えてきます
(私自身、「いざという時は、行政がなんとかしてくれるんじゃ……」と淡い期待を抱いていた時もありましたが、tasukiで防災講座を準備していく中で、「間違った期待は100%裏切られる」とバッサリ斬ってもらいました )
)
そんな中で、
「自助(市民)」と「公助(行政)」をつなぐ役割を担うのが、「共助」とのこと
自助・共助・公助、それぞれが切れ切れではなく、ひとつながりになっているんですね
【2】共助について、もっと知ろう
共助とは、「要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合うこと」だそうです。
ここで大切なのは、「私たち自身も共助の一員!」ということ
◎公助・共助の働きや、災害時の情報・物資の流れを知り、自分の立ち位置を理解すること。
◎私にできる共助とは何か、普段から心づもりをして準備し、災害時に力を発揮すること。
つまり、誰かが何かをしてくれる、ではなく、自分に何ができるのか……それを普段から意識して行動に移していくことが大切!と教わりました。
講座では、【平常時】・【災害時/直後】・【災害時/その後】とそれぞれのシチュエーション別に、私達にできる共助を具体的に説明していただきました。
(中でも私は、平常時の「自助をしっかり」・「防災訓練への参加」、災害時の「黄色いハンカチ」※「初期消火(のための消火スプレー購入)」をすぐにでも実践したいと思いますっ )
)
※黄色いハンカチとは
災害時、安否確認を迅速に行うために「我が家は大丈夫!だから他の人を助けてほしい!」という意思表示の印で、道路から見える場所に掲げるもの。黄色いものなら、ハンカチでなくてもOKだそうです。今回、講座のお土産として、黄色いハンカチを参加者にお配りしました
tasukiの講座を受講して、この黄色いハンカチを掲げることのできるママを一人でも多く増やすことができたらイイナ
その思いは、私たちが防災講座を開催し続ける原動力の一つになっています。
そして、高良さんのお話は子連れでもできる共助について、続いていきます。
時に笑いを交えつつ、分かりやすく講義してくださる高良さん。
参加者の皆さんも、時に激しく唸りながら、熱心に講義を聴いてくださいました。
マジメな話が長く続きましてので、今日の報告はここまで。
続きは開催報告②へ。
1回目のテーマは『子どもを守る部屋づくり』、2回目は『無理なくできる!日ごろからの備蓄』、3回目は『ママバッグを防災仕様に』でした。これまでの3回は、自助がテーマ。そして今回は『共助と公助・学ぼう助け合いのココロ』と題して、公助って?共助って?というところから、私達自身にできる助け合いのココロを学ぶことがテーマでした。
今回も講師は沼津市災害ボランティアコーディネーター協会災害対策委員会の高良綾乃さん。(その絶妙の語り口に、高良さんファンがじわじわ増殖中!いつもありがとうございます
 )
)講座は高良さんの講義からスタートです。
【1】公助について、もっと知ろう
公助とは何か、それを具体的にイメージできるようにお話いただきました。
主体は行政や消防になります。災害時の対応は、ライフラインの復旧や消火救援活動、また支援物資の配給などがあり、てんてこ舞い

つまり、災害時に役所や消防は、私達市民一人一人、「個人」への対応はムリ!ということが見えてきます

(私自身、「いざという時は、行政がなんとかしてくれるんじゃ……」と淡い期待を抱いていた時もありましたが、tasukiで防災講座を準備していく中で、「間違った期待は100%裏切られる」とバッサリ斬ってもらいました
 )
)そんな中で、
「自助(市民)」と「公助(行政)」をつなぐ役割を担うのが、「共助」とのこと

自助・共助・公助、それぞれが切れ切れではなく、ひとつながりになっているんですね

【2】共助について、もっと知ろう
共助とは、「要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合うこと」だそうです。
ここで大切なのは、「私たち自身も共助の一員!」ということ

◎公助・共助の働きや、災害時の情報・物資の流れを知り、自分の立ち位置を理解すること。
◎私にできる共助とは何か、普段から心づもりをして準備し、災害時に力を発揮すること。
つまり、誰かが何かをしてくれる、ではなく、自分に何ができるのか……それを普段から意識して行動に移していくことが大切!と教わりました。
講座では、【平常時】・【災害時/直後】・【災害時/その後】とそれぞれのシチュエーション別に、私達にできる共助を具体的に説明していただきました。
(中でも私は、平常時の「自助をしっかり」・「防災訓練への参加」、災害時の「黄色いハンカチ」※「初期消火(のための消火スプレー購入)」をすぐにでも実践したいと思いますっ
 )
)※黄色いハンカチとは
災害時、安否確認を迅速に行うために「我が家は大丈夫!だから他の人を助けてほしい!」という意思表示の印で、道路から見える場所に掲げるもの。黄色いものなら、ハンカチでなくてもOKだそうです。今回、講座のお土産として、黄色いハンカチを参加者にお配りしました

tasukiの講座を受講して、この黄色いハンカチを掲げることのできるママを一人でも多く増やすことができたらイイナ

その思いは、私たちが防災講座を開催し続ける原動力の一つになっています。
そして、高良さんのお話は子連れでもできる共助について、続いていきます。
時に笑いを交えつつ、分かりやすく講義してくださる高良さん。
参加者の皆さんも、時に激しく唸りながら、熱心に講義を聴いてくださいました。
マジメな話が長く続きましてので、今日の報告はここまで。
続きは開催報告②へ。
2014年11月13日
第3回ママのための防災講座 開催報告②
10/30(木)に行われた「第3回ママのための防災講座」開催報告その2です。
前半では発災後に起こりうる状況を考え、その時に何が必要になるのか?を各グループで考えました。前回のブログに引き続き、皆さんから出た意見で「おっ!」というものはこちら。
『塩(天日塩)』
下痢の後、発熱の後も水と塩があれば体調が整う。熱中症対策にも使える。
『整腸剤』
下痢は止めるより、出したり腸を整えたりする方が良い。
『ゴーグル』
避難の際に粉塵から目を守る為。災害時のホコリって侮れないようです。講師の高良さんも災害ボランティアの現場で作業用のゴーグルを着けることがあるようですが、これは横から土埃が入ってしまうそう。目を守るなら水泳用のゴーグルは完璧かも、と感想をいただきました。なかなか準備している人もいないでしょうし、見た目が斬新ですが・・・災害時に見た目の事なんて言ってられませんしね。

【3】話合いで出たグッズの中で自分が必要と思う物を書き出し、いつまでに準備するか決める。いろいろな出た意見の中で、最終的に必要か必要でないかは自分で判断してもらうのがこの講座の趣旨でした。
【4】高良さんのママバッグ公開
高良さんが普段持ち歩いているママバッグの中身を教えていただきました。
・ファーストエイド(絆創膏、マスクなど)
・万能ナイフ
・ホイッスル
・ライト・・・等々
軽く、無駄なくの工夫がされたグッズの数々。とても参考になりました!
高良さんより最後に「貸して下さい」「助けて下さい」が言えるママになって下さいとのお話がありました。「どんなに対策をしていても、現実的に子どもを連れての移動(避難)は簡単なことではありません。向かう先が同じ人がいたら、遠慮せずに荷物を持ってもらえないか声をかけてみましょう。また災害が起こってみて、足りない物がでてくるのはしょうがないことです。どうしても必要なものがある時は、他人に助けてもらう図太さも必要です。」とのこと。
私、激しく納得。「みんなが大変なんだし・・・お願いなんてできない」と考えてました。でもみんな大変だからこそ、助け合える自分でいたい!自分も誰かに対してできる事はすすんで行い、助けて欲しいことはきちんと声にできるママになろう!そう思いました。
講義はここまで。終わった後には、tasukiスタッフのバッグ(主に車に置いておくママバッグの予備的バッグ)も公開しました。小学生や幼稚園児のいるスタッフは子どもに背負ってもらうリュックを用意してあったり。少しは参考になったでしょうか・・?


今回のお土産は、亀田製菓(株)様より「ハイハイン」「ハイハインタッチ」を、興和(株)様より「マスク」(大人用、子ども用)を、Hawaiiann Relaxation LEHUA様より「アロマオイル」を提供していただきました。ありがとうございます!いずれもバッグに入れておけば災害時に役立つ物です。(アロマオイルはリラックス効果はもちろん、火傷や外傷に使えるそうです)ご協力ありがとうございました。
さて、次回第4回講座は来年開催予定です。
テーマは・・・スタッフのやってみたい事が色々ありすぎて・・・協議中です(^_^;)今回は告知が遅くなってしまい、都合がつかなかったというお声もありましたので、第4回は早め早めに動きます!次回もよろしくお願いします。
(うちだ)
前半では発災後に起こりうる状況を考え、その時に何が必要になるのか?を各グループで考えました。前回のブログに引き続き、皆さんから出た意見で「おっ!」というものはこちら。
『塩(天日塩)』
下痢の後、発熱の後も水と塩があれば体調が整う。熱中症対策にも使える。
『整腸剤』
下痢は止めるより、出したり腸を整えたりする方が良い。
『ゴーグル』
避難の際に粉塵から目を守る為。災害時のホコリって侮れないようです。講師の高良さんも災害ボランティアの現場で作業用のゴーグルを着けることがあるようですが、これは横から土埃が入ってしまうそう。目を守るなら水泳用のゴーグルは完璧かも、と感想をいただきました。なかなか準備している人もいないでしょうし、見た目が斬新ですが・・・災害時に見た目の事なんて言ってられませんしね。

【3】話合いで出たグッズの中で自分が必要と思う物を書き出し、いつまでに準備するか決める。いろいろな出た意見の中で、最終的に必要か必要でないかは自分で判断してもらうのがこの講座の趣旨でした。
【4】高良さんのママバッグ公開
高良さんが普段持ち歩いているママバッグの中身を教えていただきました。
・ファーストエイド(絆創膏、マスクなど)
・万能ナイフ
・ホイッスル
・ライト・・・等々
軽く、無駄なくの工夫がされたグッズの数々。とても参考になりました!
高良さんより最後に「貸して下さい」「助けて下さい」が言えるママになって下さいとのお話がありました。「どんなに対策をしていても、現実的に子どもを連れての移動(避難)は簡単なことではありません。向かう先が同じ人がいたら、遠慮せずに荷物を持ってもらえないか声をかけてみましょう。また災害が起こってみて、足りない物がでてくるのはしょうがないことです。どうしても必要なものがある時は、他人に助けてもらう図太さも必要です。」とのこと。
私、激しく納得。「みんなが大変なんだし・・・お願いなんてできない」と考えてました。でもみんな大変だからこそ、助け合える自分でいたい!自分も誰かに対してできる事はすすんで行い、助けて欲しいことはきちんと声にできるママになろう!そう思いました。
講義はここまで。終わった後には、tasukiスタッフのバッグ(主に車に置いておくママバッグの予備的バッグ)も公開しました。小学生や幼稚園児のいるスタッフは子どもに背負ってもらうリュックを用意してあったり。少しは参考になったでしょうか・・?


今回のお土産は、亀田製菓(株)様より「ハイハイン」「ハイハインタッチ」を、興和(株)様より「マスク」(大人用、子ども用)を、Hawaiiann Relaxation LEHUA様より「アロマオイル」を提供していただきました。ありがとうございます!いずれもバッグに入れておけば災害時に役立つ物です。(アロマオイルはリラックス効果はもちろん、火傷や外傷に使えるそうです)ご協力ありがとうございました。
さて、次回第4回講座は来年開催予定です。
テーマは・・・スタッフのやってみたい事が色々ありすぎて・・・協議中です(^_^;)今回は告知が遅くなってしまい、都合がつかなかったというお声もありましたので、第4回は早め早めに動きます!次回もよろしくお願いします。
(うちだ)
2014年11月02日
第3回ママのための防災講座 開催報告①
10/30(木)に『第3回ママのための防災講座』を開催しました!
1回目のテーマは『子どもを守る部屋づくり』、2回目は『無理なくできる!日ごろからの備蓄』でした。そして今回は『ママバッグを防災仕様に』。普段持ち歩くママバッグに+αすることで、防災力をアップさせよう!というテーマでした。
今回も講師は沼津市災害ボランティアコーディネーター協会災害対策委員会の高良綾乃さん。(無駄なく、分かりやすくお話して下さり、スタッフも頼りっぱなしです。ありがとうございました!)
講座は高良さんの講義からスタートです。
『発災後、どんなことが起きるのか?』を具体的にイメージできるようにお話いただきました。災害に対応するためのグッズにばかり目がいきがちですが、必要なものは人それぞれ。状況を把握して、その時に必要な物は何かを考えるためです。
◆屋内◆物の落下、倒壊、停電、火災、煙、ホコリ、閉じ込められ
◆屋外◆物の落下、雨風、物の倒壊、交通事故、交通マヒ、液状化、川の氾濫、津波、迷子
◆その他◆暑い、寒い、暗い、空腹、ケガ、情報混乱、不安、子どもが泣く、犯罪、トイレ
私個人的にですが、「迷子」は初耳でした。混乱を避けたり、津波から逃げているうちに道が分からなくなってしまうこともあるそう。なるほど~でした。

続いて、実際に発災後に必要になるものは何なのか、受講者の皆さんに考えて頂くワークに入ります。
【1】
決められた事は1,今、震度6強の地震が発生(会場である沼津市門池で被災)
2,24時間以内に自宅避難を目指す
3,乳幼児のママの立場で
4、自宅が津波、土砂崩れの恐れがなく、1982年以降の建物
これらの条件のもと、必要になる物を書き出す。
考え易いように、①頭や呼吸を守るもの②暑さ、寒さ対策③飲食品④衛生用品⑤情報収集⑥その他のカテゴリーに分けて考えます。
マスク、タオル、防災頭巾、毛布、お菓子、水、絆創膏、スマホ充電器、などなど・・・皆さん悩みながらもいろいろな意見を出して下さいました。

【2】
各グループ内で出た意見について話し合う。
『下痢止め薬』と意見が出たグループでは、医療関係に従事していたママさんから「止めずに出してしまう方が、身体にとっては良いので、下痢止め薬を用意するより、簡易トイレ等の対策をしっかりした方がいいのでは」なんて意見も!
スタッフで事前に話し合った時にはこの薬、大絶賛だったんですよね・・。トイレ事情が良くない災害時、できればトイレの回数を減らせたらなんて思ってました。でもこのような考え方もあるんですね~。ここでもなるほど~。
ちなみに、どちらが正解でどちらが間違ってるとかないんですよ。どちらも正解。必要なものは人それぞれですから。
これがこの講座の一番の目的。渡されたリストを基にバッグの中身を準備したとしても、全部揃えるとすっごく重いんです。中にはあれば便利だけど、あまり使わないかもという物も。それなら本当に必要な物だけを確実に持っていた方が現実的ですし、準備もし易いですよね。
皆さんで和気あいあい、時々子どもをあやしながら話合いは続きます。
続きは『開催報告②』へ。
(うちだ)
1回目のテーマは『子どもを守る部屋づくり』、2回目は『無理なくできる!日ごろからの備蓄』でした。そして今回は『ママバッグを防災仕様に』。普段持ち歩くママバッグに+αすることで、防災力をアップさせよう!というテーマでした。
今回も講師は沼津市災害ボランティアコーディネーター協会災害対策委員会の高良綾乃さん。(無駄なく、分かりやすくお話して下さり、スタッフも頼りっぱなしです。ありがとうございました!)
講座は高良さんの講義からスタートです。
『発災後、どんなことが起きるのか?』を具体的にイメージできるようにお話いただきました。災害に対応するためのグッズにばかり目がいきがちですが、必要なものは人それぞれ。状況を把握して、その時に必要な物は何かを考えるためです。
◆屋内◆物の落下、倒壊、停電、火災、煙、ホコリ、閉じ込められ
◆屋外◆物の落下、雨風、物の倒壊、交通事故、交通マヒ、液状化、川の氾濫、津波、迷子
◆その他◆暑い、寒い、暗い、空腹、ケガ、情報混乱、不安、子どもが泣く、犯罪、トイレ
私個人的にですが、「迷子」は初耳でした。混乱を避けたり、津波から逃げているうちに道が分からなくなってしまうこともあるそう。なるほど~でした。

続いて、実際に発災後に必要になるものは何なのか、受講者の皆さんに考えて頂くワークに入ります。
【1】
決められた事は1,今、震度6強の地震が発生(会場である沼津市門池で被災)
2,24時間以内に自宅避難を目指す
3,乳幼児のママの立場で
4、自宅が津波、土砂崩れの恐れがなく、1982年以降の建物
これらの条件のもと、必要になる物を書き出す。
考え易いように、①頭や呼吸を守るもの②暑さ、寒さ対策③飲食品④衛生用品⑤情報収集⑥その他のカテゴリーに分けて考えます。
マスク、タオル、防災頭巾、毛布、お菓子、水、絆創膏、スマホ充電器、などなど・・・皆さん悩みながらもいろいろな意見を出して下さいました。

【2】
各グループ内で出た意見について話し合う。
『下痢止め薬』と意見が出たグループでは、医療関係に従事していたママさんから「止めずに出してしまう方が、身体にとっては良いので、下痢止め薬を用意するより、簡易トイレ等の対策をしっかりした方がいいのでは」なんて意見も!
スタッフで事前に話し合った時にはこの薬、大絶賛だったんですよね・・。トイレ事情が良くない災害時、できればトイレの回数を減らせたらなんて思ってました。でもこのような考え方もあるんですね~。ここでもなるほど~。
ちなみに、どちらが正解でどちらが間違ってるとかないんですよ。どちらも正解。必要なものは人それぞれですから。
これがこの講座の一番の目的。渡されたリストを基にバッグの中身を準備したとしても、全部揃えるとすっごく重いんです。中にはあれば便利だけど、あまり使わないかもという物も。それなら本当に必要な物だけを確実に持っていた方が現実的ですし、準備もし易いですよね。
皆さんで和気あいあい、時々子どもをあやしながら話合いは続きます。
続きは『開催報告②』へ。
(うちだ)
2014年10月15日
『ママのための防災講座』 受講者募集!!!
定期開催しておりますtasuki主催『ママのための防災講座』。
フリーペーパー夏号、秋号の発行を挟みまして、前回の開催から5カ月も経ってしまいましたが、、、第3回を開催いたします!!!
日にちが迫っており、申し訳ありません。。。
『第3回ママのための防災講座 with tasuki 』
【主催】子育て応援サークルtasuki
【日時】平成26年10月30日(木)10:00~11:30
【場所】門池地区センター2階小会議室
【対象】子育て中のお母さんなど 20名
【託児】10名(0歳~2歳11カ月)※3歳以上のお子様は同席をお願いします。
【受講料】500円
※希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※受講できない方には10/23以降にご連絡いたします。
連絡のない方は受講可能です。
※申し込みを取り消し・キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。
【内容】
・持ち出し用バックとは?
・ママバック、車に常備しておくバックについて。
・地震が起きてからの行動シュミレーション
・ママバックを防災仕様にしよう。
・バックの中身をみんなで考えよう!ワークを実施。
など
【申込み・問合せ】子育て応援サークルtasuki
下記メールアドレス宛に、①~④の内容を明記の上、お申し込みください。
①保護者氏名②住所・電話番号③託児希望(有・無)
④託児希望の場合、お子さんのお名前(ひらがな)・年齢(○歳○ヶ月)
MAIL:staff.tasuki☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
この防災講座は、「なかなか意識を継続することが難しいけれども、小さなお子さんを抱えるママにとっては、子どもと家族を守るために大切なこと……防災。
一人では難しいけれど、一緒に楽しく学ぼう!行動に起こそう!そして、地震に強いママになろう!」そんな願いを持って、今年1年を通して、数回に分けて企画している、tasukiオリジナル講座です。
講師には、tasukiの強力な防災パートナーである高良綾乃さん(沼津市災害ボランティアコーディネーター協会所属)が全面的に協力してくださっています。
高良さんのお話は、いつも整理されていて、具体的で前向き!スタッフはいつもハッとさせられ、いい刺激を頂いています。
☆講師 高良さんのブログ http://blogs.yahoo.co.jp/ayaraccho
第1弾の講座のテーマは「子どもを守る部屋づくり」でした。
自宅で避難できるよう、その心構えから、家庭内DIGの実習、そしてアクションのポイントを盛り込んだ、充実した内容でした。(その様子はこちら☆)
第2弾は「無理なくできる!日ごろからの備蓄」
無理なくできる備蓄のポイントを座学で学び、備蓄を活用したサバイバルご飯の調理実習を行いました。(その様子はこちら☆1・☆2)
第1回目、2回目を受講された方も、受講されなかった方も、いつからでもご一緒に、私たちと防災を楽しく学んでみませんか?
皆さまからのご応募をお待ちしております!
(杉の希)
フリーペーパー夏号、秋号の発行を挟みまして、前回の開催から5カ月も経ってしまいましたが、、、第3回を開催いたします!!!
日にちが迫っており、申し訳ありません。。。
『第3回ママのための防災講座 with tasuki 』
【主催】子育て応援サークルtasuki
【日時】平成26年10月30日(木)10:00~11:30
【場所】門池地区センター2階小会議室
【対象】子育て中のお母さんなど 20名
【託児】10名(0歳~2歳11カ月)※3歳以上のお子様は同席をお願いします。
【受講料】500円
※希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※受講できない方には10/23以降にご連絡いたします。
連絡のない方は受講可能です。
※申し込みを取り消し・キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。
【内容】
・持ち出し用バックとは?
・ママバック、車に常備しておくバックについて。
・地震が起きてからの行動シュミレーション
・ママバックを防災仕様にしよう。
・バックの中身をみんなで考えよう!ワークを実施。
など
【申込み・問合せ】子育て応援サークルtasuki
下記メールアドレス宛に、①~④の内容を明記の上、お申し込みください。
①保護者氏名②住所・電話番号③託児希望(有・無)
④託児希望の場合、お子さんのお名前(ひらがな)・年齢(○歳○ヶ月)
MAIL:staff.tasuki☆gmail.com(☆を@に変えて送信ください)
この防災講座は、「なかなか意識を継続することが難しいけれども、小さなお子さんを抱えるママにとっては、子どもと家族を守るために大切なこと……防災。
一人では難しいけれど、一緒に楽しく学ぼう!行動に起こそう!そして、地震に強いママになろう!」そんな願いを持って、今年1年を通して、数回に分けて企画している、tasukiオリジナル講座です。
講師には、tasukiの強力な防災パートナーである高良綾乃さん(沼津市災害ボランティアコーディネーター協会所属)が全面的に協力してくださっています。
高良さんのお話は、いつも整理されていて、具体的で前向き!スタッフはいつもハッとさせられ、いい刺激を頂いています。
☆講師 高良さんのブログ http://blogs.yahoo.co.jp/ayaraccho
第1弾の講座のテーマは「子どもを守る部屋づくり」でした。
自宅で避難できるよう、その心構えから、家庭内DIGの実習、そしてアクションのポイントを盛り込んだ、充実した内容でした。(その様子はこちら☆)
第2弾は「無理なくできる!日ごろからの備蓄」
無理なくできる備蓄のポイントを座学で学び、備蓄を活用したサバイバルご飯の調理実習を行いました。(その様子はこちら☆1・☆2)
第1回目、2回目を受講された方も、受講されなかった方も、いつからでもご一緒に、私たちと防災を楽しく学んでみませんか?
皆さまからのご応募をお待ちしております!
(杉の希)
2014年08月28日
第2回ママのための防災講座 開催報告②
子どもたちの夏休みももうすぐ終わり!tasukiスタッフもフリーペーパー秋号の制作と第3回防災講座の準備に追われています。遅くなりましたが・・・第2回講座の後半、調理実習編の報告です。
5月13日に開催した防災講座のテーマは「備蓄」
後半はその備蓄物を活用しての『サバイバルご飯』の調理実習です。
災害が起きてからは、避難・家族との連絡・情報収集といわれる初動にかなりの時間をとられ、食事を作る気持ちにもなれない。そんな状況の中でも家族の食事をどう作るか?限られた水や材料、道具でどのような食事が作れるのか?を体験してもらいました。
【調理実習メニュー】
①土鍋ご飯で三色丼・・・コンロと鍋でご飯を炊き、缶詰や野菜をトッピング
②魚肉ソーセージ巻き・・・魚肉ソーセージを海苔で巻く
(①②レシピ提供・・日本防災士会/防災士会みやぎ 正会員 防災士 佐藤美嶺様)
③せんべい味噌汁・・・味噌をお湯で溶かし、揚げせんべいと野菜チップスを投入
(③レシピ提供・・「Date fm うちのサバ・メシ2012」レシピ集)

4つの班に別れてもらって実習スタート!テープルに置かれた材料と4リットルの水で調理~片付けまでを完了するというミッションです。
ポイントは4リットルしかない水。水を大切に、一滴もこぼすまいと皆さん工夫して調理されていました。
【参加者の皆さんから出た工夫】
・お米のとぎ汁はとっておき、野菜洗いや食器洗いに活用する
・缶詰の蓋を包丁代わりに使う(洗い物を減らす為)

・コーン缶の汁をお米を炊くのに利用(水の節約の為)
・ブロッコリーは茹でずにご飯と一緒に蒸す(水の節約の為)

・鍋の上に缶詰を置いて温める
・しゃもじ、お皿にラップをして洗い物を減らす
・使用済みラップを丸めて、スポンジ代わりにして食器を洗う
・ご飯を炊いた鍋の固まりは、水に濡らしたキッチンペーパーで覆って柔らかくする

スタッフは簡単なレシピの説明をしただけで、手順や使用する器具などは受講者の皆さんで話し合って決めてもらいました。さすがママさんたち!なるほど~と思う工夫がたくさん。どの班も与えられた4リットルの水の半分の2リットルだけで調理~片付けまでを完了させていました。
実はスタッフで前もってリハーサルをしていたんです。その時は洗剤をいつも通り使ってしまい、なかなか泡が切れずに水が足りなくなりギブアップ・・・という結果に(T_T)我々スタッフも勉強させていただきました!
【試食~各班で出た工夫を全員で共有】
・揚げせんべいが出汁の代わりになり、味噌汁が意外と美味しかった。
・初めて土鍋でご飯を炊いたが、簡単なので普段から家でもできそう。
など様々な意見を全員で共有できました。
【質疑応答】
やはり皆さんの関心は備蓄物の収納場所。ただでさえ家の中が物で溢れる子育て世帯。終了後も講師の高良さんや、ライフオーガナイザー・クローゼットオーガナイザーの縣佳子さんに質問してから帰る方が目立ちました。

※今回のテーマ「備蓄」と密接に関係する「収納」のプロである、ライフオーガナイザー・クローゼットオーガナイザーの縣佳子さんにもご協力いただきました。特に場所をとる水の保管場所についてや、ローリングストックの食材の保管方法等をアドバイスしていただきました。ブログでも講座の詳細を書いて下さっています。あがたさんのブログはこちら→『沼津・三島 毎日の洋服選びが楽しくなる!思わず見とれてしまう”うっとり”クローゼットの作り方』
【お土産】
・「揚一番」「ハイハインタッチ」(亀田製菓様よりご提供)
・「Vegips」(カルビー様よりご提供)
・「岩清水」500mlペットボトル(カクイチ様よりご提供)
・「ワンポイトイレ・バッグ収納セット」(三島市役所危機管理課様よりご提供)
講座に参加して終わりでなく、自宅に帰ってからのアクションに繋げたい、とスタッフ一同考えています。そのきっかけになれば、と調理実習で使用したお菓子を配布しました。これもサポートしてくださった企業様のおかげです!ありがとうございました!
避難生活では不便さがつきものですが、そのストレスを少しでも減らすにはやはり日頃からの備蓄、そしてホッとできる温かいご飯なんだなぁと講座を通して学ぶことができたと思います。避難生活において家族を守れるのはママです!tasukiでは『自分と自分の家族を自ら守る、地震に強いママを増やす』ためにこれからも防災についての活動を継続していきます!
『第3回ママのための防災講座』は10月中旬の開催予定!!
テーマは『ママバックを防災仕様に(仮題)』とし、防災バックの中身を検証していきます。詳細は9月に入ったらブログとFacebookでお知らせします。乞うご期待!
(うっちぃ)
5月13日に開催した防災講座のテーマは「備蓄」
後半はその備蓄物を活用しての『サバイバルご飯』の調理実習です。
災害が起きてからは、避難・家族との連絡・情報収集といわれる初動にかなりの時間をとられ、食事を作る気持ちにもなれない。そんな状況の中でも家族の食事をどう作るか?限られた水や材料、道具でどのような食事が作れるのか?を体験してもらいました。
【調理実習メニュー】
①土鍋ご飯で三色丼・・・コンロと鍋でご飯を炊き、缶詰や野菜をトッピング
②魚肉ソーセージ巻き・・・魚肉ソーセージを海苔で巻く
(①②レシピ提供・・日本防災士会/防災士会みやぎ 正会員 防災士 佐藤美嶺様)
③せんべい味噌汁・・・味噌をお湯で溶かし、揚げせんべいと野菜チップスを投入
(③レシピ提供・・「Date fm うちのサバ・メシ2012」レシピ集)

4つの班に別れてもらって実習スタート!テープルに置かれた材料と4リットルの水で調理~片付けまでを完了するというミッションです。
ポイントは4リットルしかない水。水を大切に、一滴もこぼすまいと皆さん工夫して調理されていました。
【参加者の皆さんから出た工夫】
・お米のとぎ汁はとっておき、野菜洗いや食器洗いに活用する
・缶詰の蓋を包丁代わりに使う(洗い物を減らす為)

・コーン缶の汁をお米を炊くのに利用(水の節約の為)
・ブロッコリーは茹でずにご飯と一緒に蒸す(水の節約の為)

・鍋の上に缶詰を置いて温める
・しゃもじ、お皿にラップをして洗い物を減らす
・使用済みラップを丸めて、スポンジ代わりにして食器を洗う
・ご飯を炊いた鍋の固まりは、水に濡らしたキッチンペーパーで覆って柔らかくする

スタッフは簡単なレシピの説明をしただけで、手順や使用する器具などは受講者の皆さんで話し合って決めてもらいました。さすがママさんたち!なるほど~と思う工夫がたくさん。どの班も与えられた4リットルの水の半分の2リットルだけで調理~片付けまでを完了させていました。
実はスタッフで前もってリハーサルをしていたんです。その時は洗剤をいつも通り使ってしまい、なかなか泡が切れずに水が足りなくなりギブアップ・・・という結果に(T_T)我々スタッフも勉強させていただきました!
【試食~各班で出た工夫を全員で共有】
・揚げせんべいが出汁の代わりになり、味噌汁が意外と美味しかった。
・初めて土鍋でご飯を炊いたが、簡単なので普段から家でもできそう。
など様々な意見を全員で共有できました。
【質疑応答】
やはり皆さんの関心は備蓄物の収納場所。ただでさえ家の中が物で溢れる子育て世帯。終了後も講師の高良さんや、ライフオーガナイザー・クローゼットオーガナイザーの縣佳子さんに質問してから帰る方が目立ちました。

※今回のテーマ「備蓄」と密接に関係する「収納」のプロである、ライフオーガナイザー・クローゼットオーガナイザーの縣佳子さんにもご協力いただきました。特に場所をとる水の保管場所についてや、ローリングストックの食材の保管方法等をアドバイスしていただきました。ブログでも講座の詳細を書いて下さっています。あがたさんのブログはこちら→『沼津・三島 毎日の洋服選びが楽しくなる!思わず見とれてしまう”うっとり”クローゼットの作り方』
【お土産】
・「揚一番」「ハイハインタッチ」(亀田製菓様よりご提供)
・「Vegips」(カルビー様よりご提供)
・「岩清水」500mlペットボトル(カクイチ様よりご提供)
・「ワンポイトイレ・バッグ収納セット」(三島市役所危機管理課様よりご提供)
講座に参加して終わりでなく、自宅に帰ってからのアクションに繋げたい、とスタッフ一同考えています。そのきっかけになれば、と調理実習で使用したお菓子を配布しました。これもサポートしてくださった企業様のおかげです!ありがとうございました!
避難生活では不便さがつきものですが、そのストレスを少しでも減らすにはやはり日頃からの備蓄、そしてホッとできる温かいご飯なんだなぁと講座を通して学ぶことができたと思います。避難生活において家族を守れるのはママです!tasukiでは『自分と自分の家族を自ら守る、地震に強いママを増やす』ためにこれからも防災についての活動を継続していきます!
『第3回ママのための防災講座』は10月中旬の開催予定!!
テーマは『ママバックを防災仕様に(仮題)』とし、防災バックの中身を検証していきます。詳細は9月に入ったらブログとFacebookでお知らせします。乞うご期待!
(うっちぃ)